はじめに
小学生の頃、息子は支援級の先生が担当している手芸クラブに入り、苦手ながらも楽しんで活動していました。
中学生になったら、きっと自分で選んだ部活に入って楽しむんだ──そう期待していました。
小学生時代、医師からは「てんかんを理由に教育の機会を奪わないでほしい」と手紙をいただいており、体育やプールも普通に参加していました。ですから、部活ができないのは医師の指示ではありません。
部活動への期待と現実
入学後、部活見学が始まり、息子も「どの部に入ろうかな」とワクワクしていました。
ところが、支援級の先生から「集団活動についていけていないので部活は難しい」と伝えられます。先生方も部活の顧問をしており、支援級の生徒に個別対応できない。中総体を目指して練習する部活では、本人のサポートは難しい──そんな説明でした。
試合に出なくても練習だけでも…文化部なら…という代替案はなく、「部活に入れない」という事実だけが突きつけられました。
息子に伝えると、みるみる涙を溜め「なんで…」と。号泣する姿を見て、私も胸が締めつけられるようでした。病気を持って生まれたことで「普通にできることをさせてあげられない」申し訳なさでいっぱいに。
その後も3日間、下校すると泣き続けました。きっと、クラスでみんなが部活の話をしているのを耳にしていたのでしょう。
父からの提案
3日目、夫が涙する息子を初めて見て、こう言いました。
「明日から学校の帰りに駅前の広場で5周走っておいで。1年間頑張ったら、お父さんが先生に話してあげるから」
息子の表情が少し明るくなった瞬間でした。
それから毎日、片道30分の下校途中に広場へ寄り、50メートルほどの道を5周走るように。私も途中から合流し付き添いました。
さらに、夫は息子の興味に合わせて自動でボールが出る野球練習機を購入。休日には庭で一緒に練習するようになりました。(雪でネットが潰れてしまい、今は打撃練習は休止中ですが😅)
広場ランニングから得た成長
走る習慣は、気づけば1年半も続いています。

広場の横を通る電車と並んで走り、「鉄腕DASHのリレー対決みたい!」と楽しそうに笑うことも。
続けたことで体力がつき、以前はまっすぐ走れなかったのが、まっすぐ速く走れるように。昨年の体育祭ではクラス対抗リレーで1位になり、クラスメイトから「速いね!」と声をかけられ、とても嬉しそうでした。
高校への希望
先日、息子が希望している支援学校の説明会に参加しました。そこでは「中学まで部活に入れなかった子どもが多く、高校で初めて部活を経験したい」という思いからソフトボール部を立ち上げ、今では県代表として試合に出場していると伺いました。
見学した部活動はどれも生き生きとしていて、仲間と目標に向かって活動する姿に感動。
ソフトボールでなくても、陸上や文化部でも、息子が仲間と励む高校生活がきっと糧になる──そう強く思いました。
おわりに
障害児育児では「道が制限されること」もあります。
でも、それは先生が冷たいからではなく、集団を支えるための現実的な事情もあるのだと思います。実際に、支援級では息子が楽しんで学べるよう工夫していただき、できることが増え、自信もつきました。
小学生の頃は登校を渋ることが多かった息子が、今では朝一番に学校に着きたいと早く家を出るように。先生方の温かい受け入れに感謝しかありません。最近は、早く登校して体育祭の長縄跳びの練習に参加させてもらっているそうです。
障害児を育てていると、制限や悲しさに直面することも多いです。
でもそれ以上に──先生やドクターの応援、友達の優しさ、そして息子自身が困難を乗り越えようとする姿から、私は「優しい世界」を見せてもらっています。
そして、私ももっと優しくなりたいと思うのです。
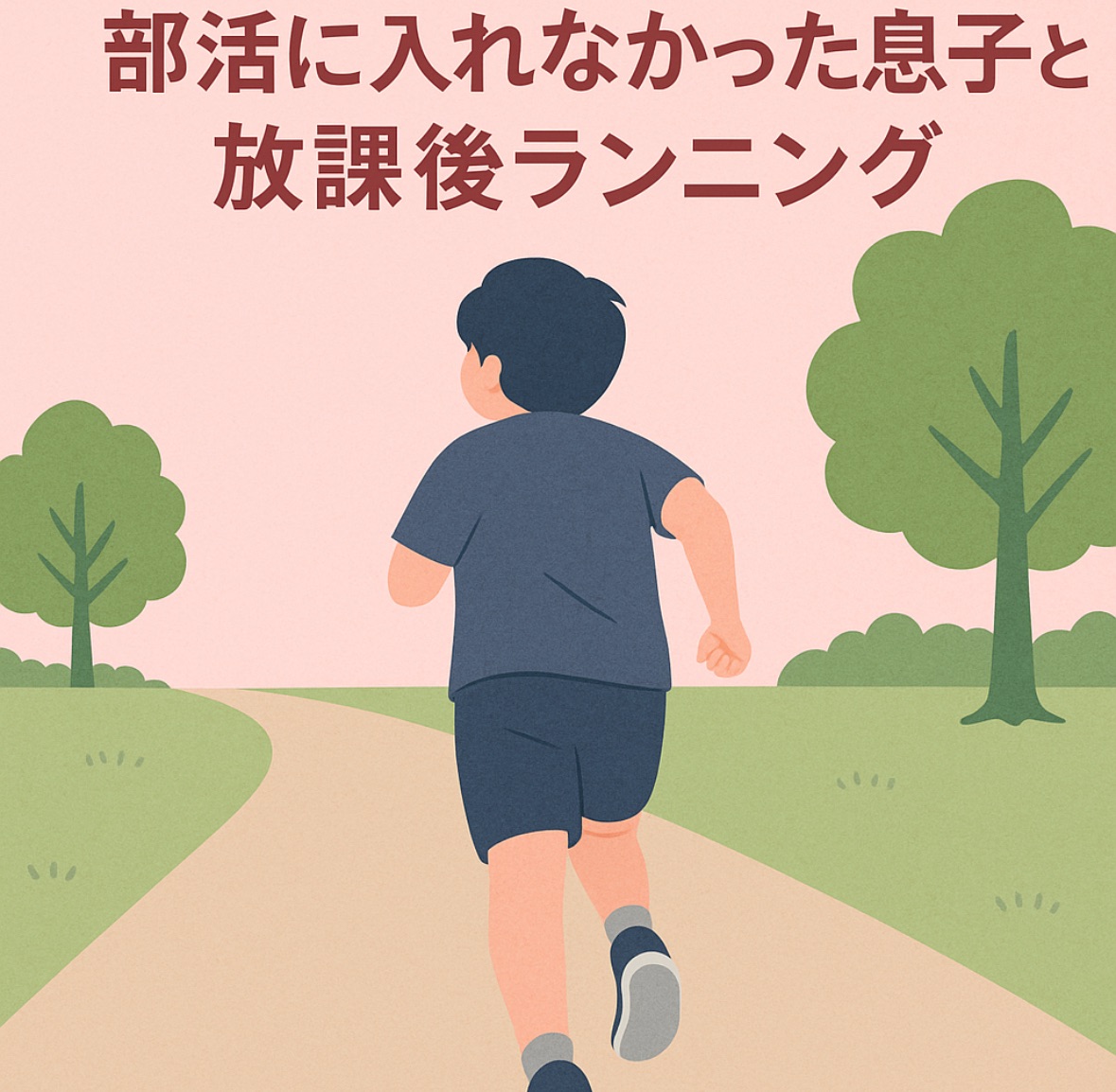
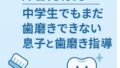

コメント